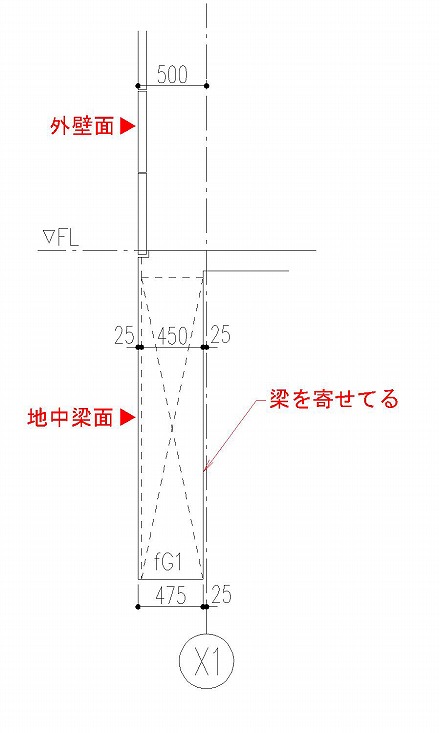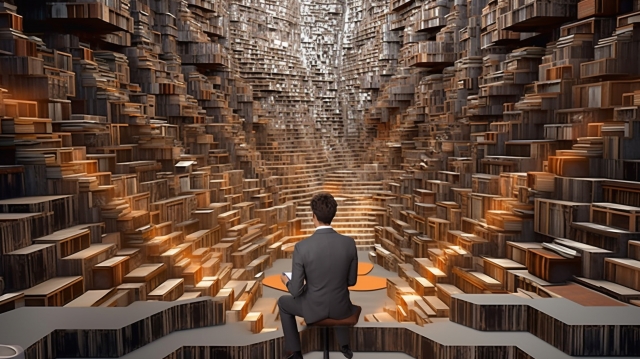このカテゴリーでは、建築施工図の中でも特に「躯体図」について色々と説明をしてきました。
「杭伏図」については大体説明が終わりましたので、次に説明するのは杭の上に施工する「基礎」についてですね。
基礎は杭に比べて項目が少し多いです。
説明もそれにつれて長くなっていきますし、私の説明力で上手いこと説明出来るかは不安ですが…
そんなことを書いても始まらないので、まずは基本的な部分からはじめましょうか。
■基礎ってそもそも何?
基礎とは何か?どんな種類があるのか?
そんな素朴な疑問についてまずは調べてみると…まずは大きく分けて2種類あることが分かります。
・杭基礎
・直接基礎(独立基礎・布基礎・べた基礎)
今までは杭について説明してきたので、その際に出てきた基礎というのは当然「杭基礎」ということになります。
それ以外の「直接基礎」の場合、当然ですが杭を必要としない構造である訳で、杭伏図は不要ということになります。
表層が既に固い地盤である場合や、建物の荷重があまり大きくない場合などなど…
杭が必要ない構造は結構あって、そうした場合には直接基礎が採用される訳ですね。
何度も書いている気がしますが、建築というのは本当に様々な工法があって奥が深い。
ただし。
建築施工図を作図する我々の役割は「杭基礎か直接基礎かを比較して考えること」ではありません。
それは構造設計者の役割ですから、別に悩む必要はなく、ただ色々ある種類について知っておくだけで大丈夫です。
建築施工図を作図する際には、もう既に検討された結果として基礎構造が構造図に記載されていますから。
構造図に杭が記載されていれば「ああ、今回は杭基礎か…」ということで、杭伏図と基礎伏図を作図する。
構造図に杭が記載されたいなければ「直接基礎ね…」という感じで基礎伏図を作図する。
建築施工図の作図者が担う役割はそこです。
基礎の構造について知っておきべきではありますが、そこで悩む必要はないんです。
もちろんもっと深い知識を持っていた方が良いに決まっていますが、建築施工図を作図する為に必要な知識はもっと別のところにあります。
なので、まずは建築施工図に必要な知識から積み上げていき、余裕が出たら構造についてもっと深く勉強していきましょう。
で、とりあえず簡単に説明をすると…
今まで説明してこなかった直接基礎ですが、基本的な考え方はあまり変わりません。
建物の荷重を地盤に伝える役割を持っていて、それが深い場所にある為に杭を使うのか、そうでないのか。
そんな違いがあるだけです。
敷地内の地盤状況については、構造図にボーリング柱状図があるので、それを見れば支持層がどこにあるかは分かります。
杭基礎の場合は杭の下端が、直接基礎の場合は基礎の下端が、それぞれ支持層に到達しているはずです。
考え方としては、ここまで知っておけば多分問題ないはずです。
という訳で、基礎の種類についてここでこれ以上詳しい説明をするのはヤメにしておきます。
次回はまず「杭基礎」について説明をしていきましょうか。