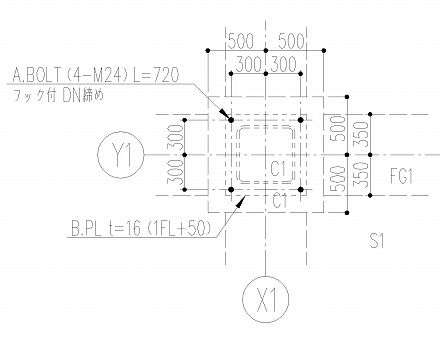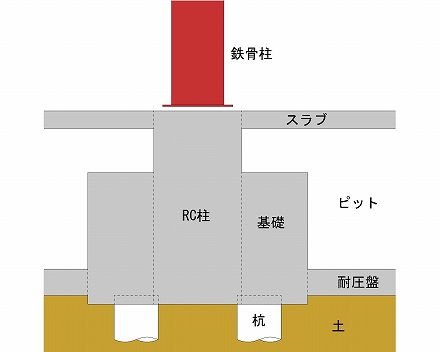鉄骨柱の足元と、地下のコンクリートを連結するためには、一般的にどのような手段が採用されるのか。
前回はそのあたりの話をして、鉄骨柱の足元に取り付けるベースプレートという部材を紹介しました。
コンクリートに埋め込んだアンカーボルトの頭が少し出ていて、それがベースプレートの孔に通る。
そしてアンカーボルトにはネジが切ってあって、ボルトを締めつけて固定をする、という手順になります。
このあたりの納まりは、普段何気なく利用している駅のホームなどで、よく見るとたくさんあります。
電車を待っているだけの空いた時間などに、興味を持って色々と見てみると面白いですよ。
という現物はさておき、今回はそれを躯体図にどのように表現をするのか、実際に例を出して説明してみます。
■躯体図に必要な情報
建築施工図の中で、躯体図というのは基本的にコンクリート工事をする際に見られる図面です。
というのは今さらですけども……
実際に使われる図面ですから、コンクリート工事をする際に「何かやっておく必要があるもの」は全て書いておく必要があります。
躯体図に書いていないことは、現場で施工されることはない。
そんな気持ちを持って、コンクリートを打設する前に用意していくことがないかを考え、躯体図を書いていく必要がある訳です。
考えてみると結構そういう要素がありますが、ここではとりあえずアンカーボルトとベースプレートの表現を考えてみたいと思います。
アンカーボルトはコンクリートに埋め込む訳ですから、コンクリートを打設する前には絶対にセットをしておくべき部材です。
これを躯体図に表現しないということは、「アンカーボルトを埋め込まなくても良いですよ」と言っているのと同じ。
それでは構造体が成立しないので、躯体図が果たす役割は重要なんですね。
と言うことで、基本的な考え方だけを書いていても仕方がないので、具体的な話に進みましょう。
■床伏図に記入
鉄骨柱のアンカーボルトをどの躯体図に表現するかというと、今まで全く説明をしてこなかった「床伏図」です。
床伏図は「ゆかぶせず」と読みます。
私の記憶では、このサイトではじめて登場した言葉ですね…説明の途中で新しい言葉が出てきました。
ちょっと予想外の展開というか、説明の順番が全然思い通りに出来てない状態で申し訳ありません。
後で詳しく説明するとして、ここで簡単に書くと「床伏図」というのは各階の床情報を表現した躯体図です。
断面図で見てみると、このあたりを切って見下ろした平面という感じ。、
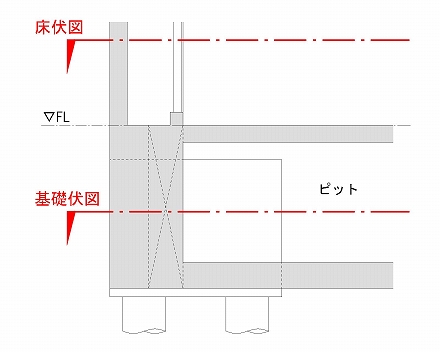
基礎伏図と比べてみるとよく分かると思います。
コンクリートの壁があれば切断面として見えてきて、あとはコンクリートの床が見えてくるというイメージですね。
床に段差があったりすれば、それも見えてくることになって、そのあたりの情報を表現する図面になります。
床面から少しアンカーボルトが飛び出している訳ですから、表現をする図面の種類としては床伏図が適切、ということですね。
そんな床伏図に、どのようにアンカーボルトを表現していくのか、という内容については次回に続きます。
なかなか自分で思った通りに説明が進みませんけど、少しずつ着実に進んでいるはず…どうか最後までお付き合いください。