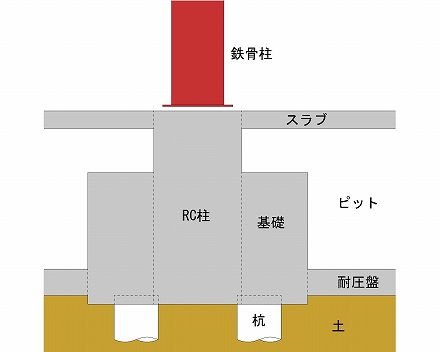躯体図を書く手順として、杭伏図の杭天端レベルを確認するところまで話が進んで来ました。
杭の天端レベルを決める為の要素は基礎のレベルであり、基礎のレベルは設計図通りではなく、仕上を考慮して確認をすること。
これを守れば、杭伏図はもう完成したのと同じです。
あとは自分で確認した数値通りの躯体図を作図していけば、杭伏図は表現すべき項目が少ないので、割とすぐに完成します。
これはもうCADの操作だけの話ですよね。
そうした作図はそれほど重要ではなく、数値を決めるまでのプロセスが何よりも重要である。
これが分かれば、躯体図を書くプロに一歩近づいたはずです。
■支持層について考える
杭は支持層に1m以上貫入すること。
構造図を見ると、そうした表現がどこかに必ず記載されているはずです。
なぜこんな表現があるのかというと、支持層のレベルが実際にどうなっているか、正確には分からないから。
支持層がどの程度のレベルにあるかは、あくまでもボーリング柱状図で読みとるしかないものです。
敷地の広さにもよりますが、ボーリング調査をするのは敷地内で5ヶ所とかそのくらい。
そこで分かったN値50以上の地盤レベルで、実際には掘ってない部分の支持層レベルも想定するんです。
だから当然、それが間違っているというリスクはあります。
部分的な範囲で、急激に支持層レベルが下がっているとか、そういう状況は実際に施行してみないと分かりません。
構造図に記載されているのは、あくまでも「杭の長さ」と「想定杭下端レベル」でしかないんです。
それにプラスして「支持層に1m以上貫入」と書かれているので、そのどちらかの条件を満たす、という逃げがある訳です。
■躯体図にもただし書きを
構造図をベースにした躯体図である杭伏図も、支持層については、当然構造図が書かれた時以上の情報はありません。
だから杭伏図にも、別に逃げる訳ではありませんが、同じ表現をしておく必要があります。
「杭の下端レベルは想定で、実際には支持層に1m以上貫入させること」みたいな表現を。
これはずるい表現だと言われる場合も、もしかしたらあるかも知れません。

でも、躯体図の作図者である我々が考えて支持層が分かるなら別ですが、そうではないですよね。
考えても誰も分からないことだから、「もしかしたら違う可能性もありますよ」という表現をしても良い、と私は考えています。
ただ、特に既製コンクリート杭などの、工場で造って現場に搬入するタイプの基礎であれば、想定以上に支持層が深いとお手上げなんですよね。
決まった長さの製品ですから、それを現場で伸ばすことは誰にも出来ませんから。
躯体図では簡単に伸ばすことが出来ますけど、実際現場に現物があるのなら、それを伸ばすのは不可能ですよね。
既製品にはそういう怖さがある為、どうしても「ちょっと長めの杭にしておこう」という気持ちになります。
長さが足りなくなることを考えれば、多少長い杭を打ち込むことになったとしても、はるかに手間は少ないですから。
現場打ちのコンクリート杭であっても、結局は落とし込む鉄筋の長さが変わってしまうので、簡単に深くすることは出来ません。
支持層のレベルというのは、そういう意味で考えると、杭のレベルに多大な影響を与えることになるんですね。