コンクリートで造った地下部分と、鉄骨で造る地上部分を連結するには、どんな手段があるのか。
前回はその話をするつもりが、いつの間にか「建物の寿命」みたいな話になってしまいました。
長い期間変わらずに建ち続ける建物とする為には、やはりしっかりとした構造体を造る必要がある。
そういう意味では全然無関係な話ではないから、まあ良いかな。
今回は鉄骨の柱とコンクリートの柱を連結する具体的な手段について、図を交えて説明したいと思います。
■アンカーボルトとは
コンクリートと鉄骨。
特徴の異なる2つの部材をつなぎ合わせるには、コンクリート側と鉄骨側で、お互いに連結する為の準備が必要です。
これは両方連結する為の準備をしておく必要があって、片方だけが準備をしていても連結は出来ません。
ということで、まずはコンクリート側がどんな準備をしておくべきか、という話から。
コンクリート側では、一般的に鉄骨柱を取り付ける為に、アンカーボルトと呼ばれる鉄の棒を埋め込んでおきます。
アンカーボルトを埋め込んだ後でコンクリートを流し込み、ガッチリと固めてしまう訳ですね。
もちろん全部埋め込んでしまったら、普通の鉄筋と同じような話になってしまうので、頭の部分を少し出しておきます。
少しだけ頭を出しておいた部分と、鉄骨柱側で準備しておいた形状を組み合わせて連結をする、という流れになります。
イメージはこんな感じ。
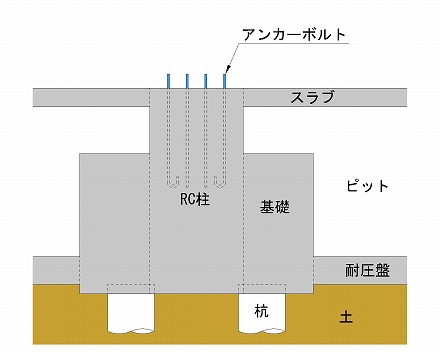
■アンカーボルトの表現
これはアンカーボルトがコンクリートの柱に埋め込まれ、頭だけ少し出ている状態を断面図で描いたものです。
もちろんアンカーボルトの他も、ここでは表現していませんが、柱とか基礎、そして地中梁の鉄筋が埋め込まれます。
柱や梁の鉄筋とアンカーボルトを組み合わせて、そこでガッチリと固定する、というようなイメージです。
鉄骨柱が倒れる方向に力がかかった時、アンカーボルトがそれを支える事になる訳です。
鉄骨の柱がどの程度の大きさなのか、何階建ての建物なのか、などによってアンカーボルトの仕様は変わります。
どれくらいの太さの物を使うのか。
何本のアンカーボルトを埋め込むのか。
コンクリートにはどのくらいの長さ埋め込むのか。
これらの情報は、それぞれの柱仕様とセットになって、構造図に必ず記載されています。
躯体図を書く際には、鉄骨柱の足元がどのように納まるのか、というのをイメージしながら作図することになります。
そして、コンクリート躯体図ですから、コンクリートに埋め込む物はきちんと表現しておく必要があります。
・埋め込むのは平面でどこになるのか
・どんな仕様のアンカーボルトを埋め込むのか
これらを説明しておかないと、コンクリートを打設した後で「あ、アンカーボルトを埋め込み忘れた」という情けない状態になってしまいます。
こうなると建築現場に与える影響は非常に大きくなるので、そういうことにならないよう、躯体図にはしっかりと表現をしておきましょう。





