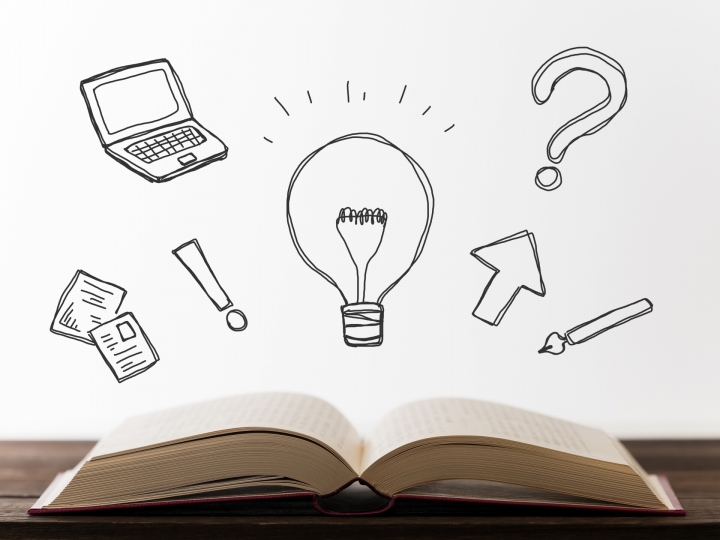前回は設計者の役割について書いたので、今回はその相手となる施工者について、その役割などを書いてみます。
施工図を作図するということは、立場としては施工者側の一員ということになる訳です。
まあ何となく「施工者」という字を読めば分かる気もしますが…簡単にいってみますか。
■ゼネコン
施工者というのは、一般的にはいわゆる「ゼネコン」と呼ばれる会社を指すことが多いです。
スーパーゼネコンと呼ばれる大手5社(大林・鹿島・清水・大成・竹中)をはじめ、たくさんのゼネコンがあります。
町を歩いていると時々建設現場を見かける事がありますが、入り口の看板などを見るとゼネコンの名前はすぐに分かります。
そんな施工者の役目は、以下の項目をそれぞれ満たしつつ、請け負った建物をきちんと完成させること。
・設計図書の意向に沿った建物であること
・法律に沿った建物であること
・定められた品質基準を満たしていること
・契約した工期を守ること
・安全に作業を進めること
・出来るだけコストを抑えること
施工者として工期を守るのは当たり前のことですが、それを安全に行いなおかつ利益を出す必要がある訳です。
求められる品質を維持しつつコストを抑える。
この辺に矛盾を感じますが、施工者は高い技術と豊富な知識を頼りにそれを実行していきます。
実際間近で見ていて凄いなと良く思います。
■施工図の役目
コストだとか性能などの制約が多い建築現場の中で、施工図は割と重要な道具になって来ます。
まずは基本ですが、間違いのない施工図であることが重要ですよね。
基本的に現場は施工図の通りに作られますので、設計図書に書かれている内容を守っていないようではまずいです。
後々で現場を直す事になると、何の為の施工図で事前に検討しているの?…という話になってしまいます。
そして当然余分にお金がかかる事になりますので、施工図を作図する際にはそういった間違いをなくす必要がある訳です。
そのあたりの内容を押さえた上で、さらに法や定められた品質を守った内容になっていること。
これが施工図に求められる品質です。
それと、工事工程にあったタイミングで施工図を作図していく必要もあります。
前回簡単に説明した、設計者の承認までにかかる時間を考えると、事前に図面を作図するのがキツかったりもします。
が、それでも何とか施工図を作図しなくてはなりません。
どうも施工図の大変な部分だけを強調してしまいましたが、それでもやりがいのある仕事だと思いますよ。
…ものは言いようなだけかも知れませんが。