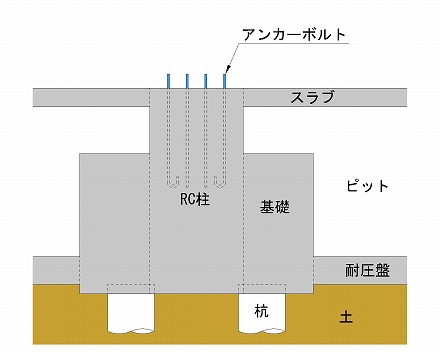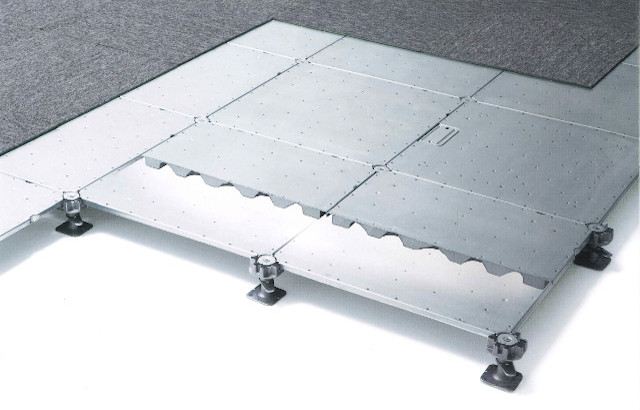躯体図を書く為に気をつけることを説明しようとして、今まで私が経験したことを色々と書いてしまいました。
おかげで全然具体的な話が出来ていませんけども…
設計図に書かれていることだけを盛り込んだ躯体図では、現場が満足することはない、ということは伝わったかな。
これから憶えようとすることに対し「なぜそんなことを考える必要があるのか」を知っておくこと。
これは結構重要なことだと思うので、少し話が長くてもまあ良いんじゃないか、と、勝手に考えています。
■説明の順番について
さて。
いくら私の失敗した話が無駄ではないとは言っても、毎回同じような話をしている訳にもいきません。
私はそれでも何となく文章を書いていくことが出来ますけども、実際そんな話はあまり面白くないのですよね。
それに、似たような話をしていても全然役に立たないので、そろそろ具体的な話をしていきましょう。
どうやって具体的な説明をしていくのか悩みますが、躯体図の書き方手順まとめに書いた手順に沿って説明をしてみます。
その法が説明する私にも読む側にも分かりやすいですよね。
作図手順に沿って、この際にはこんなことに気をつけて躯体図を書いていけば良いか、どんな事を検討していくべきか。
設計図通りだけではない躯体図をまとめる為に必要な要点。
そのあたりの話を順番に色々と書いていきますので、最後まで読んでみてくださいね。
■通り芯の入力
ということで、まずは最初の項目である「通り芯の記入」ですが…まあこれはあまり問題ないですよね。
通り芯は設計図に書かれているのと同じ間隔で、そのまま素直に作図をすれば全然問題なく終わります。
ただ、設計図のデータをそのまま使うというのは、私としてはあまりお勧めすることが出来ません。
設計図のデータが完全に正しいかどうかは、設計図を作図していない我々には分かるはずがないから。
躯体図を書く際には、通り芯というのは全ての基準となる非常に重要な要素になります。
それをただ単に設計図から貼り付けて終わりにするというのは、まあ好みの問題もあるでしょうけど、私は好きじゃないんですよね。
もう少し細かい話としてCAD的な問題を挙げるとすると、設計図の通り芯が微妙に水平垂直ではない可能性がある、ということ。
私は一度、せっかくデータがあるのだからということで、設計図の通り芯を貼り付けて利用したことがあります。
その際に運悪く設計図の通り芯が本当に微妙に傾いていて、しかもそれに気がついたのが、躯体図を書いてかなり経った時でした。
当時はオートキャド(AutoCAD)で躯体図を書いていて、通り芯を基準にしたオフセットコマンドを多用していました。
オートキャド(AutoCAD)のオフセットコマンドというのは、あらかじめ作図してある線に平行な線を引くコマンドです。
その「あらかじめ作図してある線」が通り芯で、その通り芯が本当に微妙な角度になっているとしたらどうなるか…
想像して頂ければ分かると思いますが、躯体図に作図されたほぼ全ての線が、少しずつ斜めになっている、ということになりました。
そんな状態になった躯体図をどう直せば良いのか。
色々と考えましたが、基準になる通り芯でさえ水平垂直ではない中で、全てを修正することなんて出来ませんでした。
まあ躯体図の書き直しですね。
そういう残念なことにならないよう、躯体図の基準となる通り芯は、ぜひ自分の手でゼロから作図することをお勧めします。
設計図のデータを利用するのは、通り芯の作図が終わった後です。
設計図のデータをCAD上で重ねて見て、寸法が間違いがないかチェックする為に利用する程度にしておきましょう。