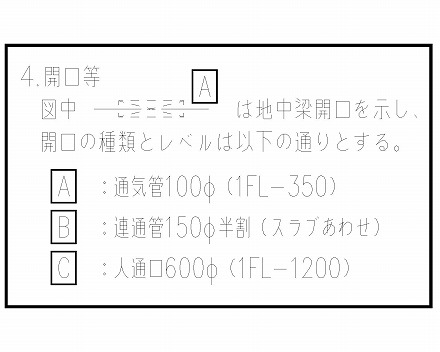「構造体」というのは、建築施工図を作図する際、特に躯体図を作図する際に良く出てくる言葉です。
建物の骨組みを造る上で欠かせない躯体図。
詳しくは他のカテゴリーで説明をしていますので省略しますが、躯体図を作図する上で「構造体」は非常に重要な要素なんです。
これを知っておかないと怖くて作図が出来ない、というくらいに。
とは言っても、それほど難しい話でもありませんので、今回はこの「構造体」について説明していきます。
■絶対に守るべきもの
今このページを読んでいる方が、躯体図の作図手順についてどこまでの知識を持っているかによって説明の仕方も変わってくる。
…とか考えていたのですが、躯体図の作図手順を熟知している人が「構造体って何だろう…」ってなるはずないですね。
という訳で、割と最初の方から説明をしていきます。
建築施工図というのは、基本的に設計図書をベースにして作図をしていくのが大前提になります。
もちろん納まりとかコストなどの問題がある為に、全部が設計図の通りになるわけじゃないです。
しかしそれでも、大きな方針としては設計図がベースになることに違いはありません。
そして、躯体図のベースになる設計図は構造図です。
構造図では、建物骨組みをどのようにすれば地震や台風に耐えうる建物になるかがが検討されます。
様々な力に耐えられるような建物となるよう構造計算などが行われ、その構造には細心の注意が払われるんです。
そうして発行された構造図には、どの位置にどんなサイズの柱や梁を配置するかが細かく書かれていることになります。
もちろん外見だけの大きさだけではなく、どの程度の太さの鉄筋を何本配置するかも書かれています。
これらの仕様は建物の骨組みとして検討された内容ですから、躯体図を作図する際に絶対守らなければならないポイントとなります。
・柱のサイズと鉄筋の仕様
・梁のサイズと鉄筋の仕様
・床の厚さと鉄筋の仕様
この、構造図に記載されている、躯体図を作図する際に守らなければならない建物の骨組みを「構造体」と呼ぶんです。
例えば柱について考えると、1階から2階の間にある柱の仕様が「C1」だったとします。
そして柱リストを見ると、C1という柱のサイズが800×800だったと仮定しましょう。
その場合、最終的にどれだけ柱が大きくなったとしても、800×800の部分が構造体ということになります。
そのサイズの範囲には、構造図に記載されている鉄筋がしっかりと配置されています。
コンクリートは鉄筋と組み合わさることで。はじめてその強度やねばり強さを発揮します。
だから、鉄筋が配置される「構造体」が、建物の骨組みとして非常に重要な要素である訳ですね。
完成した柱のサイズが構造体よりも大きい分には、要求された性能を満たしている訳ですから問題はありません。
でも、構造図に書かれている柱サイズよりも小さい柱だった場合には、要求された性能を満たしていないことになり…
最悪の場合は地震時に建物が崩壊することにもなりかねません。
確か以前ニュースで、構造体の鉄筋が少なくて危険な為、住むことが出来ないマンションが問題になりました。
その時は躯体図で構造体のサイズを間違えた訳ではなく、ベースとなるべき構造図から強度が不足していた訳ですが…
同じような話になってしまわないように、構造図に書かれた構造体のサイズはしっかりと守って躯体図を作図する。
基本的な話なのですが、躯体図を作図する上で絶対に守るべきことですので、しっかりと覚えておきましょう。