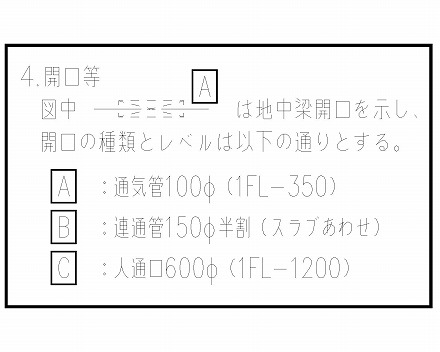建物が建つ場所の地盤がどのような状態なのか、というのは、建物の構造を考える上で結構重要な要素です。
このサイトで扱っているのは建築施工図についての情報ですから、建物の構造をどうするかに悩むことはありません。
が、建築施工図には「杭伏図」がありますので、まるっきり無関係という訳じゃないんですね。
杭のレベルを考える上で、地盤の固さを表す「N値」は欠かすことの出来ない要素なんです。
知識として知っておいて損はないと思うので、ここでさらっと概要だけ掴んでおきましょう。
■何回打ち込んだか
まずは結論から書いてしまうと、N値というのは地盤の固さを表す数値です。
N値が大きいほど地盤は固く締まっていて、建物の重量を支えることが可能と判断されます。
一方N値が小さいと、地盤は軟らかく建物の支持層には成り得ません。
一般的には地表に近い程地盤は軟らかい事が多く、深く掘っていけば高い地盤が出ることが多いです。
もちろんこれは場所によって大きく変わってきますが、50程度あれば充分に固い地盤と言えます。
ここまでは良いとして、ではN値の数値はどのように計測するのか。
数値が大きい=固い地盤
数値が小さい=軟らかい地盤
ということですが、実はこの数値というのは叩いた回数を意味しています。
地盤調査をする際には、筒状のもの深い場所まで打ち込んで調べる訳ですが、ではどうやって打ち込むのか。
原理は金槌で釘を打ち込むのと同じで、おもりを上からがつんと叩いて少しずつ打ち込んでいくんです。
釘を打ち込む場所が発泡スチロールだと、きっと1回で釘は全部打ち込む事が出来ます。
でも固い木の釘を打ち込もうとした場合、何度も金槌で釘の頭を叩く必要がありますよね。
もちろん地盤が相手でもそれは一緒。
固い地盤の時は打ち込むのに回数を要し、軟らかい地盤の時は何度も叩かなくても打ち込むことが出来ます。
という訳で、簡単にまとめると…
N値というのは、決められた装置を一定の距離だけ地盤に打ち込むのにかかる回数なんです。
だから固い地盤ほどN値が大きく、軟らかい地盤ほどN値が小さい。
決められた装置の詳細とか、どれくらいの距離を打ち込むのかとか、そういう難しい話は後でOKです。
まずはこの基本的な考え方を掴んでおきましょう。
■もう少し具体的に
最初はここまでの知識で充分だと思いますが…
情報をお伝えする側として、ここで終わることは出来ませんので、具体的な数値も以下に記します。
63.55kgのハンマーを76cm落下させ、標準貫入試験用サンプラーを地盤に30cm打ち込むのに何回かかったか。
具体的な数値を出すとこのようになりますが、まああまり憶えても意味がない数字だと私は思ってます。
また、同じN値でも、粘土層と砂層とで少し違いがあったりとか、かなり奥が深い世界です。
でも、少なくとも建築施工図を作図する上では、そうした細かい知識はそれほど役には立ちません。
もちろん知っておいた方が良いに決まってます。知識は多いに越したことはありませんから。
でも、建築施工図のプロになる為には、N値の詳しい求め方を憶えるより先に憶えるべきことがたくさんあるんです。
N値については概要を知っておく程度にとどめ、もっと建築施工図に直結することを当サイトでは書いていきたいと思います。